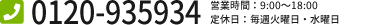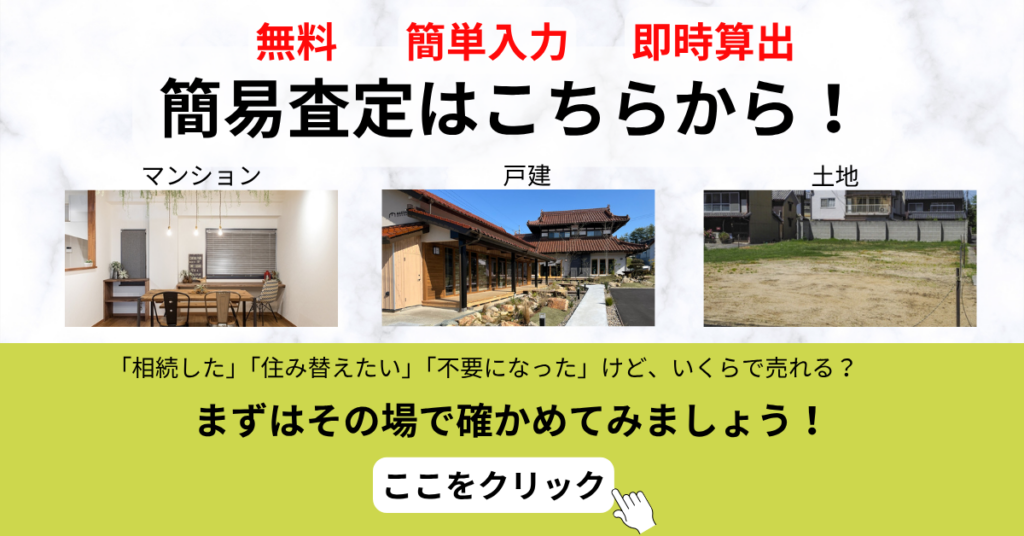中古住宅の売却にかかる諸費用とは?
内訳・相場・節約のコツを徹底解説
中古住宅の売却には、仲介手数料・登記費用・税金などのさまざまな費用がかかります。 売却価格だけでなく、「手取り額」をしっかり試算することが大切です。
■中古住宅の売却時にかかる主な諸費用一覧
| 項目 | 内容 | 金額の目安・計算方法 |
| 1.仲介手数料 |
不動産会社に支払う報酬 |
売却価格×3%+6万円+消費税(上限) |
|
2.登記関連費用(抵当権抹消など) |
抵当権の抹消や名義変更のための手続き費用 | 登録免許税:1件1,000円+司法書士報酬(1~3万円前後) |
| 3.印紙税 | 売買契約書に貼る収入印紙代 | 売買価格により変動 |
|
4.譲渡所得税 (必要な場合) |
売却益が出た場合の税金 |
所得税+住民税 (短期or長期で税率が異なる) |
| 5.住宅ローン残債 | 売却時に一括返済が必要 |
残債全額+繰上返済手数料 (金融機関による) |
| 6.引っ越し費用 | 売却後の転居に伴う費用 | 数万円~ |
|
7.修繕・リフォーム費用 (任意) |
物件の印象を良くするための 整備費用 |
数万円~ (内容による) |
| 8.ハウスクリーニング費用(任意) | 内覧前に清掃を依頼する場合 |
3~15万円程度が相場 (内容による) |
| 9.解体費用 | 更地にして売却する場合 | 木造住宅で100万~200万円程度 |
各費用の詳細解説
1.仲介手数料
売却を不動産会社に依頼した場合に支払う成功報酬です。
計算式:【売却価格 × 3% + 6万円】+消費税
例)2,000万円の売却なら
2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円 + 消費税
2.登記関連費用
住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要がある場合、その手続きに費用がかかります。
登録免許税:1件につき1,000円
司法書士報酬:1万~3万円が相場
3.印紙税
売買契約書を作成する際、契約金額に応じた印紙税を支払う必要があります。
契約金額, 印紙税(軽減措置適用後)
~1,000万円以下, 5,000円
~5,000万円以下, 1万円
~1億円以下, 3万円
4.譲渡所得税(※利益が出た場合のみ)
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
・保有期間5年以下:短期譲渡所得 → 約39%(所得税30%+住民税9%)
・保有期間5年超:長期譲渡所得 → 約20%(所得税15%+住民税5%)
※特別控除(3,000万円の特別控除)や買い替え特例が適用されるケースもあるので要確認。
5.住宅ローンの残債
売却時にローンが残っている場合は、一括返済が必要です。 また、金融機関によっては繰上返済手数料が発生する場合もあります。
6.引っ越し費用
新居への移転に伴う費用です。繁忙期・距離・荷物の量によって異なります。
目安:5万〜15万円程度
7.修繕・リフォーム費用(任意)
売却前に壁紙やフローリングを張り替えたり、設備を修繕したりすることで売却価格がアップする可能性もあります。 ただし「やりすぎ」には注意。
8.ハウスクリーニング費用(任意)
内覧の印象を良くするため、プロに清掃を依頼することも検討材料に。 キッチン、浴室、トイレなど水回り中心で約3〜8万円が目安。
9.解体費用(古家付き土地の場合)
更地での売却を希望される買主が多い場合、売主が解体費を負担することも。 木造なら坪4~6万円程度が一般的。
■諸費用をなるべく抑えるためのポイント
中古住宅の売却で諸費用をなるべく抑えるためのポイントは、以下の通りです。費用を抑えることは「手取り額の最大化」につながるため、実践できる部分から検討してみてください。
諸費用を抑えるための7つのポイント
① 抵当権抹消を自分で手続きする
司法書士に依頼せず、自分で法務局に手続きすることで報酬(1~3万円)が節約できます。抵当権抹消は比較的難易度が低いため、チャレンジ可能です。(但し、取引案件によってはできないこともあります)
② 印紙税の軽減措置を確認する
国税庁が定める軽減措置の適用期間中であれば、印紙税が通常より安く済みます。契約書の金額区分によって金額が変わるので、契約内容を確認しましょう。
③ 譲渡所得税を抑える特例を活用する
利益が出た場合の譲渡所得税には、以下のような控除があります。
特例 内容
・3,000万円特別控除 自宅を売った場合、最大3,000万円まで課税されない
・買換え特例 住み替え先を一定期間内に購入すると課税を繰り延べ
・空き家譲渡特例 相続空き家を売却する場合に適用される控除(最大3,000万円)
税理士や税務署に事前に相談し、適用条件をチェックするのが安心です。
④ハウスクリーニングや修繕を自分で行う
専門業者に頼むと数万円かかりますが、自力で対応すれば費用を削減可能。内覧時の印象をよくするため、最低限の掃除や補修は効果的ですが、大規模なリフォームは費用対効果が悪いため慎重に。
⑤ 引っ越し費用を比較・節約する
複数社から見積もりを取って比較することで、安い業者が見つかることも。平日・閑散期(1〜2月、6〜8月)に引っ越すと費用が下がる傾向があります。
⑥ 解体費用は買主に負担してもらう交渉もあり
古家付き土地を売却する際、「現状渡し(解体は買主負担)」で交渉すれば費用がかかりません。「古家付き」として価格を下げて売り出す方が、結果的に早く・安く済むこともあります。
削減できる費用は抑えつつも、印象アップのための最低限の清掃や税制優遇を活かすための申請、信頼できる仲介業者の選定など、「費用対効果」を見極めることも大切です。
■中古住宅売却の節税方法
中古住宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税や住民税がかかります。しかし、一定の条件を満たすことで、大幅に税負担を軽減できる「節税制度」が用意されています。下記では、中古住宅を売却する際に活用できる主な節税方法をご紹介します。
1.3,000万円特別控除|居住用不動産の売却で適用
もっとも多くの方が利用するのが、「マイホームを売った場合の3,000万円特別控除」です。これは、自宅を売却した際に発生した譲渡所得から最大3,000万円までを控除できる制度で、実質的に税金がかからなくなるケースも多くあります。
【主な適用条件】
・売却した物件が自分の居住用である
・売却から3年以内に住まなくなった物件も対象
・配偶者や親子など特別な関係の人に売却していないこと
2.長期譲渡所得の軽減税率|10年以上所有した自宅なら
マイホームを「10年以上所有」していた場合、所得税や住民税の税率が軽減される「軽減税率の特例」も活用できます。通常は約20%(所得税15%+住民税5%)の譲渡税が、約14%(所得税10%+住民税4%)に引き下げられます。
【ポイント】
・所有期間は「引渡日の属する年の1月1日時点」で判定されます
・所有期間が10年超かつ居住用であることが条件です
3.特定居住用財産の買い換え特例|住み替え時に有効
マイホームを売却して新しい住まいを購入する場合は、「買い換え特例」により、売却益への課税を繰り延べることができます。ただし、いずれは課税されるため、節税というよりは課税のタイミングを先送りする制度です。
【主な条件】
・売却物件が自宅であること
・売却の1年前~1年後までに新居を購入
売却額 ≧ 新居の購入額であること(売却額 ≦ 新居の購入額の場合はそもそも税金がかかりません)
4.相続空き家の3,000万円特別控除|相続で取得した家を売るときに
相続で取得した空き家を売却する場合も、条件を満たせば「3,000万円特別控除」を受けられます。
【対象となる物件の例】
・昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅
・相続後に誰も住んでいない、又は事業として使用していない又は貸付けていない
・売却額が1億円以下
解体後の更地での売却も対象になる場合があります。
5.譲渡損失の損益通算と繰越控除|売却損でも節税できる
売却によって損失が出た場合でも、一定の条件を満たすと、その損失を他の所得(給与など)と相殺できる「損益通算」や、翌年以降に繰り越して控除する「繰越控除」が適用されます。
【活用の例】
・マイホームの売却で損が出た
・新たな住宅をローンで購入している
節税には「確定申告」が必要です。ご紹介した節税制度は、確定申告を行うことで初めて適用されます。 制度の利用には、売却した不動産の情報や住民票、取得費用・譲渡費用の証明など、複数の書類が必要です。不安な場合は、税務署や税理士に相談するのがおすすめです。
■中古住宅の売却に関するご相談はマエダハウジング不動産へ
中古住宅を売却する際は、単に売却価格だけでなく、「最終的にいくら手元に残るか」が重要です。節税制度を正しく理解し、早めに準備を進めることで、不要な税負担を避け、手取り額を最大化することが可能になります。「自分の場合はどの特例が使えるのか知りたい」という方は、お気軽にマエダハウジング不動産までご相談ください。